reserve
![]()

鎌倉府=関八州(.相模/武蔵/上野/下野/上総/下総/安房/常陸)+ 伊豆/甲斐
足利将軍家(室町幕府/中央政権)は各国に守護職を任命し、その守護大名が国を管理する(今で言う知事みたいなもの)。ただし、関東地方は荒くれ坂東武者を管理するため、鎌倉に「府」を設け、関東公方(鎌倉公方とも称す)を任命する。そして、関東公方を補佐する武士の頭領として関東管領職を置く。その管領職は上杉家が任ぜられる。山内家・扇谷家・犬懸家・詫間家などなど分家の多い上杉家だが、格段に勢力を誇示していたのが山内家と扇谷家でこの二家を「両上杉家」とも呼ぶ。本来なら補佐し、補佐される信頼関係にあるべき「関東公方」と「関東管領」の関係が機能しない。また本来なら一族の結束が求められる「両上杉家」も険悪な関係になりつつあった。
◎年代で表す関東の戦国時代
1.永享の乱 永享10年(1438)~永享11年(1439)
鎌倉公方足利持氏が中央政権に抗い、関東管領山内上杉家・扇谷上杉家と抗戦。公方持氏の自害で終結する。
2.享徳の乱 享徳3年(1455)~ 文明14年(1483)
鎌倉公方足利成氏(持氏の遺児)が関東管領の山内上杉憲忠を暗殺、再び公方家が山内上杉家・扇谷上杉家と抗戦。戦いの形勢が不利となった成氏は鎌倉から古河に拠点を移す(以後は古河公方と称す)。敗北濃厚となった成氏は中央政権と和議「都鄙合体」を結び28年間に渡って関東の国人たちを二分させてきた乱が終結する。
この乱では古河公方を承認しない中央政権が新たな公方足利政知を関東に派遣するも、関東の戦乱を前に箱根を越えることは出来ずに伊豆の堀越に居館を構えた。「堀越公方」の誕生であり、関東には2つの公方が生れる形となった。
◆長享元年(1487) 北条早雲、京から駿河国へ下向(駿河守護 今川家当主の正室は早雲の姉)
3.長享の乱 長享元年(1487)~永正2年(1505)
関東管領山内上杉家と扇谷上杉家が抗戦、18年にも及ぶ戦いは再び関東の国人たちを二分させる大乱となる。戦いの理由などなく、要はどちらの上杉家が時代のリーダーなのか...ただそれだけである。不毛の戦いであり、関東の大地を疲弊させる以外の何物でもなかった(古河公方家は存在感を発揮できず)。
◆明応2年(1493) 北条早雲、伊豆堀越御所を襲撃(堀越公方家、歴史の表舞台から退場)
◆明応4年(1495)か 北条早雲、箱根を越えて小田原城を攻略
◆永正元年(1504) 北条早雲、扇谷勢の武将として立川原の戦いに参戦
4.長享の乱終結 永正2年(1505)
この戦いが北条家の関東進出を容易にさせる結果ともなった。長きの戦乱で両上杉家も関東国人も疲れ果て、関東の大地は不毛の土壌で覆われる。
戦国時代、関八州(相模、武蔵、上野、下野、上総、下総、安房、常陸)に覇を誇ったのが小田原城を本拠とした北条家です。北条家は初代早雲から始まり2代氏綱、3代氏康、4代氏政、5代氏直と続いたため、私たちは「北条五代」と呼んでいる。ときは戦国の世、室町幕府の権威は失墜し、その影響は地方にも及ぶ。関東も例外ではなく、関東地方を統括する「関東公方」と「関東管領職」の権威は崩れた。乱れた世に突如として現れた男たちは、伊豆の国を奪うと、箱根の山を越えて相模の国小田原に進んだ。そして、武蔵国・相模国の実力者である扇谷上杉家に真っ向から戦いを挑む。男たちの勢いは止まらず、「関東管領職」山内上杉家にもその矛先を向ける。世は乱れるも、家名が重んじられるのは日の本の国の性(さが)か。どこの馬の骨とも分からぬ男たちが関東の地を荒らすのは、「狼藉者」と変わらぬ所業だ。男たちもそのことを知っている。だからこそ名乗りを変えた。その昔、関東では源頼朝が鎌倉に幕府を開いた。そして源氏に代わって、幕府の権威者となったのが執権「北条氏」だった。我らは北条氏の血筋を引く。関東の秩序を守るのが我らの使命だ。男たちは何の所縁(ゆかり)もない北条家の姓を名乗る。後世の史家は鎌倉幕府の執権「北条家」との差別化(=違い)を図るため、男たちのことを「後北条氏」と呼んだ。「小田原北条家」=「後北条氏」=「北条五代」は関東の覇者への道を進む。ときには甲相駿三国同盟を結んで背後を守り、とにきは上杉謙信と戦い、そして織田信長の不運にも助けられ、関八州の夢物語を紡いでいく。やがて信長の遺産を奪い取った豊臣秀吉が関白となり、日の本の統一を図る。その「関白」秀吉が裁定を下した領土の境目を北条家は破った。そして「関白」秀吉が全国に発した小田原北条攻めによって、関東王国を夢見た男たちの物語は終わりを告げた。

五代の当主の簡単な足跡は下のリンクから飛べます。
▼
![]() そううん
そううん
![]() うじつな
うじつな
![]() うじやす
うじやす
![]() うじまさ
うじまさ
![]() うじなお
うじなお
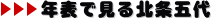 準備中
準備中
■北条早雲 生年未詳~永正16年(1519)8月15日
一介の素浪人で、今川家の居候....長く伝えられてきた北条早雲の素性ですが、実際の北条早雲は身分正しき備中伊勢家の出自でした。また姉が駿河今川家(駿河源氏)の当主の正室ですから、それだけでも格式ある身分であったことは分かります。駿河今川家の当主義忠が合戦の流れ矢を受けて命を落とす。今川家は後継者をめぐって家中が混乱する。その頃、京都で室町将軍家に仕えていた早雲は姉北川殿の願いを受け駿河に下向し、混乱する家中をまとめる。その功績から今川家より禄を受け駿河に滞在しました(姉と当主となった甥を見守るのも目的か)。やがて興国寺城主となった早雲が目を付けたのは、堀越公方足利茶々丸の暴政で乱れた伊豆の国であり、その伊豆の国を奪うや、次いで箱根を越え相模国に進んで小田原城を攻略します。ときには今川家の命を受けて出陣をしたり、ときには関東の権威者に従うなど、早雲は奇妙な立ち位置を保ちながら北条家の地盤を固めていきました。そして永正16年(1519)、伊豆韮山城にてその波乱に満ちた生涯を閉じます。なお、北条早雲は「北条」姓を名乗っていません。本名は伊勢新九郎盛時(長氏とも)と伝えている。
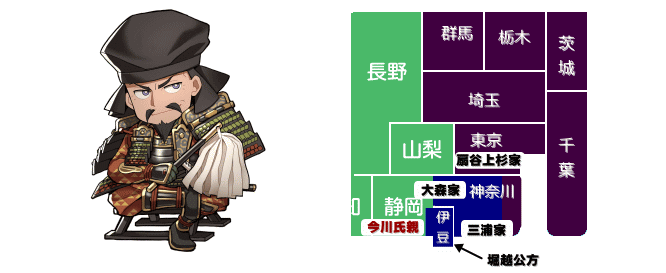
※紺色は北条家の支配権を指している。
※黒字は敵対、赤字は同盟国(早雲の時代の今川家は主君みたいなもの)
(イメージ画像:北条早雲「©北条五代観光推進協議会」)
■北条氏綱 長享元年(1487)~天文10年(1541)7月17日
戦国大名として自立し(今川家と敵対関係へ)、本城を小田原に移し、家名を「北条」姓に変えたのが北条氏綱でした。時代を切り開いた初代早雲の圧倒的な名声と、3代氏康の優れた領国運営の狭間で印象が薄い2代氏綱です。しかし、北条家を戦国大名として基礎を固めたのは、紛れもなく氏綱でした。また、ときの関東の権威者である関東管領山内上杉家と扇谷上杉家に真っ向から挑み、多摩川を越えて現在の東京都に勢力を拡大していくのも2代氏綱の時代であり、ついには扇谷上杉家の本城河越まで手中に収めました。そして、小弓公方を旗頭に掲げ、江戸湾を越えて対決姿勢を示す里見家と言う新たな宿敵の登場にも負けてはいません。その小弓公方を討ち滅ぼすと、今度は関東武者の心の拠り所である鎌倉の鶴岡八幡宮の再建に乗り出します。この意味することは、まさに北条家が関東管領職を担い、関東公方足利氏と結び、関八州を支配することにあるのではないでしょうか。あまりにも有名な「勝って兜の緒を締めよ」は氏綱の訓戒が語源です。関東の戦乱の主人公に躍り出た北条家ですが、氏綱は多くの戦いを通して「勝ち続ける」ことの怖さを知りました。そして、鎌倉八幡宮の造営工事が完成した翌年の天文10年(1541)に55年の生涯を終えています。
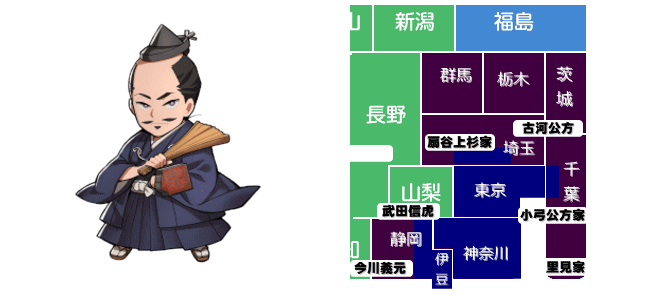
※紺色は北条家の支配権を指している。
※黒字は敵対、赤字は同盟国
(イメージ画像:北条氏綱「©北条五代観光推進協議会」)
■北条氏康 永正12年(1515)~ 元亀2年(1571)10月3日
北条家の隆盛を築き上げた知勇兼備の名将として、その評価は不動とも言える。(異説はあれど)河越夜戦での戦いぶり、戦国史の二大英雄とも称される武田信玄・上杉謙信とともに、関東三国志の一角を担った史実、そして武蔵国(東京/埼玉)の国人たちを服属させ、その版図を上野や下総にまで拡げていく。そして甲斐/駿河との間に締結した甲相駿の三国同盟も忘れてはならない。北条氏康と言う人物像を確かなものにするには、十分過ぎる手腕である。しかし、何よりも氏康を氏康たらしめているのは、この時代に最も優れた領国経営を本拠地小田原に確立させたことにある。このことに異存を挟む人はいなのではないか。検地や税制改革を推進、職人使役のための公用使役制の採用、そして伝馬手形の発給機構の改革などを打ち出していく。合わせて独自の官僚機構を創出し、その中では訴訟制度の改革も行っている。これらの集大成として「小田原衆所領役帳」の完成が挙げられようか。この役帳は、一族と家臣の諸役賦課の基準となる役高を記した分限帳であり、家臣に対する軍団編成のあり方などが示されている。現在では北条氏の研究に欠かすことのできない一級品の史料ともなる。氏康はこの役帳を仕上げると家督を氏政に譲り、自身は「御本城様」として当主氏政の後見に当たった。
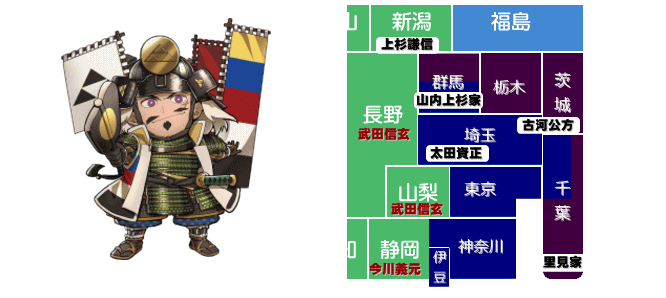
※太田資正は扇谷上杉家に従っていた武蔵の国人(岩槻城主)。
※紺色は北条家の支配権を指している。
※黒字は敵対、赤字は同盟国
(イメージ画像:北条氏康「©北条五代観光推進協議会」)
■北条氏政 天文7年(1538)~天正18年(1590)7月11日
時代を見誤った4代当主。大勢を見間違えたとも言われている。所詮、人は結果論で語られるのか。お家を潰すと言うことは、まさにその典型なのだろう。嘘か真か、ご飯に掛ける味噌汁の逸話まで後世に語り継がれる始末だ。それなら、戦国乱世の時代に家中を固くまとめた手腕は評価されないのだろうか。関八州に里見家や佐竹家ら宿敵が健在していた時代に、武田信玄や上杉謙信、織田信長、徳川家康と言う名将英雄が共に生きた時代に、北条家は一族一門だけでなく、重臣までもが固く結束して“こと”に当たった。そして、北条家の勢力を拡大維持し、関東に覇権を誇る。諸国の戦国大名家を見たときに、これほど一門家中が固く結束して戦国の世を戦い抜いたお家があったのだろうか。そして、その王国の頂きに座していたのは、北条氏政その人である。勿論、豊臣秀吉との折衝は批判されても致し方ない。中央政権との外交政策を誤った責任は氏政にあるのは否定しない。しかし、それだけで氏政と言う人物を語っては何も見えてこないのではないか。「小田原評定」は決して無意味な話し合いの時間・会議ではない。この時代、最も優れた領国経営と評された北条家にとって、「小田原評定」はその根幹を成した需要評決機関であったことを、僕らは声を大にして語っていかなければならない。
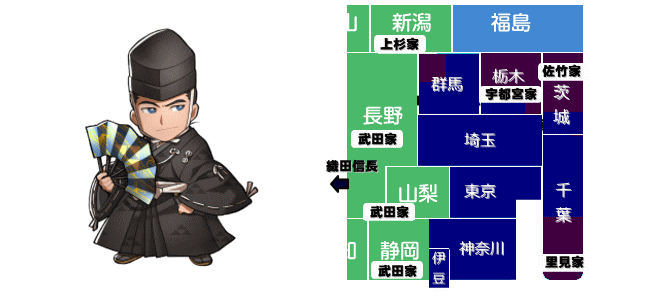
※紺色は北条家の支配権を指している。
※黒字は敵対、赤字は同盟国
(イメージ画像:北条氏政「©北条五代観光推進協議会」)
■北条氏直 永禄5年(1562)~天正19年(1591)11月4日
北条家の最後の当主として、歴史にその名を残すこととなった。しかし、当主としての実績は残せたのだろうか。氏直を思うときに、僕はいつもそのことを考えてしまう。既に関東地方における北条家の基礎は固められ、その管理と運営の手腕を、氏直のお手並み拝見と言うときに豊臣秀吉率いる天下の軍勢が小田原を囲む。「もはやこれまで」と4カ月に渡る籠城から小田原の城を開く(降伏)。その決断を下したのが氏直だとしたら、彼が残した最大の業績とも言えるのではないか。御本城様として父である氏政が背後に控えていた。北条軍団の副将とも伝える叔父の氏照の存在も大きい。それまでの治世、軍議で北条家の当主として決断を下せることがあったのか。小田原の開城で多くの城兵の命が救われた。だが、父氏政と叔父氏照は詰め腹を切らされ、自分は生き残った。北条家と言う「お家」を潰した苦悩、父と叔父を救えなかった自身の非力さに心が蝕まれる。高野山に追放の身も、正室の父徳川家康の仲介もあってか秀吉から罪を許された。これから新しき北条家の歴史を作り出していく。これから真の当主として....しかし、若き氏直の心の苦しみは、そのまま彼の肉体までを蝕んでいた。享年30歳、あまりにも若すぎる死だった。死因は疱瘡と伝えている。豊臣秀吉がその罪を許し、幕下の諸大名の一人として北条氏直を迎えようとしたのだから、何かしらの光を放っていたのかも知れない。
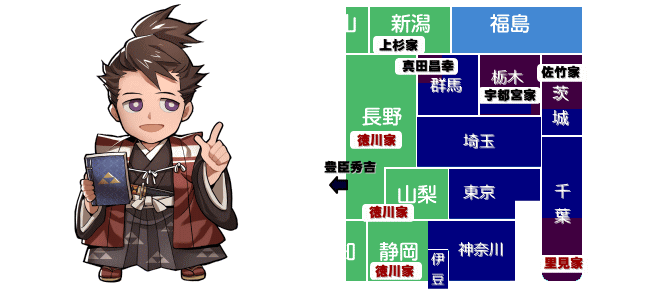
※真田家は武田家に従っていた信濃の国人。武田滅亡後、戦国大名家として自立。
※紺色は北条家の支配権を指している。
※黒字は敵対、赤字は同盟国
(イメージ画像:北条氏直「©北条五代観光推進協議会」)
