reserve


![]()
![]() 伊豆 堀越御所
伊豆 堀越御所
古河公方の関東統治を認めない室町幕府が、新たに関東に送った足利政知を祖とする。しかし、関東の戦乱の激しさで進むこともままならず、堀越(伊豆国韮山)に留まる。正式な関東公方の発令もないなどその影響力は伊豆一国でしかなかった。政知の子茶々丸のとき、北条早雲の侵攻で滅ぼされる。
![]()
![]() 相模 小田原城
相模 小田原城
駿河国東部(駿河郡藍沢原)から興った土豪と伝えられる。鎌倉公方に従い功を挙げ、のち相模小田原に進出すると扇谷上杉家の重臣として勢力を誇示していく。戦国史の中でも名高い北条早雲による小田原城攻略で大森家は滅んだとされるが、一族の中で北条氏に従って家名を紡いだ者もいるようだ。
![]()
![]() 相模 岡崎城 → 相模 新井城
相模 岡崎城 → 相模 新井城
鎮守府将軍平良文にも繋がる名家とも言えるが、鎌倉時代に執権北条氏によって滅せられた。のち傍流の三浦佐原氏によって再興される。戦国期は扇谷上杉家の重臣として大森氏と並んで相模国内に勢力を誇った。しかし、北条早雲の侵攻で城に籠もって防戦も、三年にわたる籠城戦の末に玉砕し滅んだ。

![]()
![]() 武蔵 江戸城 → 武蔵 河越城
武蔵 江戸城 → 武蔵 河越城
鎌倉の扇ガ谷に居館を構えたことから扇谷上杉と呼ばれた。南関東に勢力を誇示するも古河公方家や山内上杉家との対立を続ける。北条家の関東侵攻で江戸城、次いで河越城を奪われ、その最後は河越夜戦での敗北で滅した。早雲、氏綱の代のとき、扇谷上杉家は関東進出の上で巨大な壁でもあった。
![]()
![]() 上野 平井城 → 越後 御館
上野 平井城 → 越後 御館
鎌倉の山内に居館を置いたことから山内上杉と呼ばれる。代々に渡って関東管領職を継承してきた家柄だが、古河公方との対立や分家「扇谷上杉家」との戦いに明け暮れる。北条家の関東進出で扇谷家と休戦し、ともに北条勢に戦いを挑むが、最後は居城平井を奪われ越後に逃走する。そして、管領職と名跡を越後守護代の長尾氏に譲渡した。
![]()
![]() 下総 古河公方館
下総 古河公方館
室町幕府が関東統治のために任じた鎌倉公方がその源となる。足利持氏のとき、関東の統治権を中央政権にと画策する幕府と対立、その子成氏の代になって古河に居を構えたことから古河公方と称された。北条家との対立や関係修復を繰り返すも、足利義氏の代になると北条家のお飾り/傀儡でしかなかった。
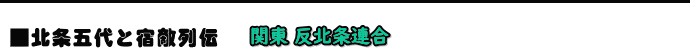
![]()
![]() 上総 久留里城
上総 久留里城
安房を拠点に勢力を拡大し、小弓公方を旗頭に北条家とも敵対する。一方で内紛も絶えず、北条家の助力を得ることもあったようだ。江戸湾を挟んでの北条家との攻防は続くも、のちに北条家優位の形で同盟を結ぶこととなる。所領は削られながらも秀吉の時代は生き残れたが、江戸時代になって改易された。
![]()
![]() 下野 宇都宮城 → 下野 多気山城
下野 宇都宮城 → 下野 多気山城
平安時代の摂政関白藤原道兼にルーツを求める関東の名門。北関東に安定した地位を誇っていたが、のちに宿老たちの反発などで家中が混乱する。北条家の北関東侵攻に際しては、上杉謙信の関東越山に呼応する形で佐竹家らと反北条の立場を明確に示す。その後、豊臣秀吉より突然の改易処分が発せられた。
![]()
![]() 常陸 太田城
常陸 太田城
源氏の名門。戦国期の当主義重は「鬼義重」の異名で常陸の大半を支配下に置く。上杉謙信の関東越山に呼応し、反北条の一翼を担うが北条勢との直接の対決は少なかった。豊臣秀吉に重宝されるも、関ヶ原では徳川家に敵対する形となり、戦後は出羽秋田に減封となる。
![]()
![]() 武蔵 岩付城 → 常陸 片野城
武蔵 岩付城 → 常陸 片野城
扇谷上杉家の重臣。主家滅亡後、一度は北条家に従うも上杉謙信の関東越山を機に反北条へ転じ、北条家の幕下に留まる実子と袂を分かつ。以後、上杉謙信と関東諸将の間を取り持つも、常陸の佐竹家に比重を置く態度から謙信の反発も買う。秀吉の北条攻めに参陣するも、旧領岩付への復帰はなかった。
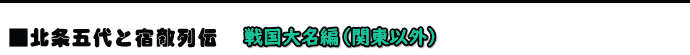
![]()
![]() 駿河 府中館
駿河 府中館
源氏の名門。北条氏綱の時代に対立はあったが、北条家とは親密な関係でした。甲相駿の三国同盟も、当主義元が桶狭間で織田信長に討たれると、その機に乗じた武田信玄が同盟を破棄し今川領に侵攻します。北条家の助勢も駿河・遠江の領土を失い、戦国大名家としては滅亡する。江戸期は高家として将軍家に仕える。
![]()
![]() 甲斐 躑躅ヶ崎館
甲斐 躑躅ヶ崎館
源氏の名門。武田信虎の時代に今川家と同盟を結び、北条家と険悪になるも武田信玄の時代になって三国同盟を結ぶ。しかし、その同盟が崩れると北条家との戦いが激化する。一時、再び同盟を結ぶも武田勝頼の時代になって関係が悪化する。織田・徳川連合軍との戦いで甲斐源氏武田家は滅した。
![]()
![]() 越後 春日山城
越後 春日山城
越後守護代長尾家が、関東管領上杉家の管領職と名跡を譲られ「上杉家」になる。北条家の関東侵攻を良しとはせず、反北条の武将たちに請われ幾度となく関東に越山する。上杉謙信没後、その跡目争いと影響で精彩を欠くも、豊臣秀吉に接近し重宝される。不識庵謙信公の家柄か、家康より家名の存続が許される。
![]()
![]() 信濃 上田城
信濃 上田城
信濃の国人で、武田家の信濃侵攻でその幕下に降る。以後、信濃先方衆として信を得る。主家武田の滅亡後は戦国大名として自立、徳川・上杉・北条の巨大勢力に囲まれながらも巧みな外交術で生き残っていく。上野国沼田領を巡る北条との戦いが、天下人秀吉を巻き込む形でそのまま北条家滅亡の道へと繋がっていく。徳川の時代も家名は存続する。

![]()
![]() 近江 安土城
近江 安土城
戦国の風雲児か、それとも革命児か。優秀な家臣団を従え、美濃や近江、そして京を抑えて天下人の一歩手前まで登っていく。その威光を前に北条家も臣従を願い出るも、武田討伐の際の北条家の不甲斐なさから信長の怒りを買う。北条家の存続の危機も、本能寺の変で救われる結果となった。織田家の家名は豊臣、徳川の世も続き明治を迎える。
![]()
![]() 摂津 大阪城
摂津 大阪城
百姓(半農半士)の子も織田信長に従うなかで家臣団の頂点まで登り詰め、信長亡き後はその遺産を奪い取る形で天下人「関白」の称号まで得る。北条家に対して再三に渡って上京して挨拶=臣従を求めるが、北条家は答えない。そして、秀吉の裁定(仲介)を破った北条家に堪忍袋の緒も切れ、討伐軍を率いて小田原に出陣する。秀吉没後、江戸期の大阪の陣で豊臣家は潰える。
![]()
![]() 遠江 浜松城
遠江 浜松城
今川家からの自立、織田信長との同盟、豊臣秀吉へ臣従と言う歴史の中、家臣団と領国をまとめて確実に力を蓄える。信長亡き後、その遺領である甲斐と信濃を巡って北条家と合戦になるも、相互に領土への不可侵を約して同盟を結ぶ。娘(督姫)は5代氏直の正室となる。秀吉亡き後の関ヶ原合戦で天下人に。
