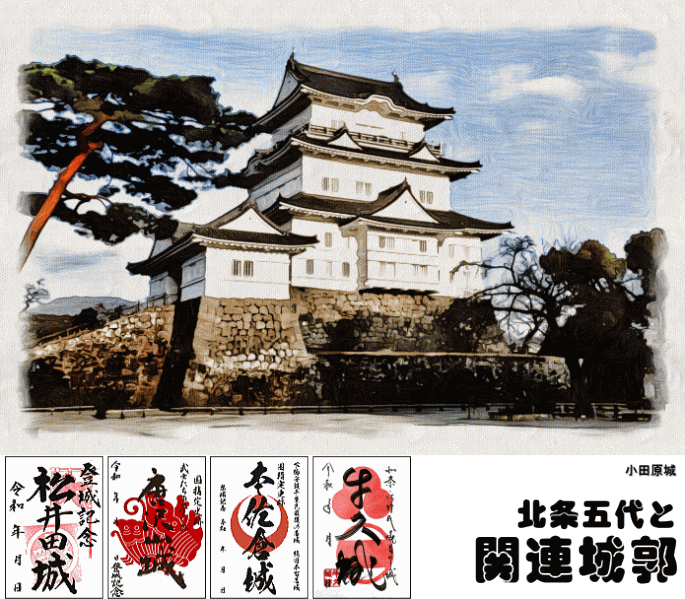
城の数だけ彼らの夢がある。
広げてみた関東の地図には、その夢が詰まっていた。
多分に血の匂いが感じられるも、
ときの流れがその悲しみを癒してくれる。
だから、今度の休日は彼らの夢の跡を訪ねてみたい。

 古城は左側に並ぶバナーから進んでください(まだまだ途中ですが)
古城は左側に並ぶバナーから進んでください(まだまだ途中ですが)
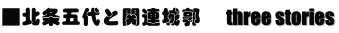
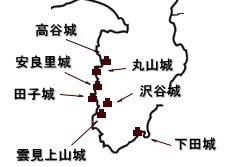 北条水軍の要 西伊豆地方
北条水軍の要 西伊豆地方
北条家は水軍にも力を注いでいたと思われ、各地にその足跡を伝えている。江戸湾を挟んで対峙する里見家を睨む浦賀城や三崎城(共に神奈川県)が良く知られているが、駿河湾を望む西伊豆の水軍拠点も忘れてはならない。仮想敵国は駿河の今川家であり、甲斐の武田家である。伊豆国の国人たちは北条早雲の伊豆侵攻でその臣下となった。そこで北条家は彼ら伊豆の国人たちの才能を活かし水軍の整備に努めた。観光地で有名な下田市の下田城だけでなく、西伊豆沿岸には富岡氏の高谷城や丸山城、梶原氏の安良里城、山本氏の田子城、渡辺氏の沢谷城、高橋氏の雲見上山城らの水軍城が築かれていた。しかし、一部の城を除いて古城そのものには見るべきものもなく、恐らくだが船を係留する入り江の整備に力を入れていたのではないだろうか。お金は無限じゃないからね^^街中や住宅地の城なら分かるが、城の遺構が何も残されていないとは考え難い。

北条流築城術の妙技 畝堀と障子堀
甲州流築城術と言う言葉があって、甲斐の武田家の築いた城に見られる独特な構えになるんでしょうか。織豊期の築城は織田信長や豊臣秀吉の時代、要は戦国最盛期の頃に築かれた城を指すのでしょうね。我が北条家にも独特な構えがありまして、最も知られているのが「畝堀」と「障子堀」ですね。静岡県の三島市に残される山中城はその典型と言いますか、北条流の美学が詰まった古城址になります。「畝堀」も、「障子堀」も堀底に仕切りが入ります。城の堀は曲輪を守る防御であって、攻め手の移動を阻害する。しかし、その一方で堀底道と言う言葉あって、堀の底は通路にもなるんですね。北条家の独特な堀はその堀底に仕切りを入れることで攻め手の自由な移動を阻止しました。それでも山中城は豊臣勢の攻撃であっけなく落城しました。どんなに防御を固めようが、最後は「人は城、人は石垣」になるのでしょうか。

小田原から群馬/栃木/茨城は遠いぞ!
関東地方の古城、言うなれば北条家に関りがあった古城を回りながら疑問に思ったことがある。彼らの狙いが関東地方の統一にあるとしたなら、何故その居城を小田原に固執したのだろうか。背後の駿河今川家との関係は悪くない。油断ならぬ男、甲斐の武田信玄が控えているとは言え、小田原はあまりにも西に偏り過ぎている。織田信長は、その目的に向け何度も居城を変えている。本城を移すと言うことは、とてつもない労力と決断が必要であると言うことは分かるが、東京都中央区や埼玉県川越市あたりに本拠を構えた方が、関東の政(まつりごと)と攻略には便利だと思うが、それは素人の浅はかな考えなのか。それでも思う、北条家に欠けているカリスマ性は何だったのか。それは織田信長のように時代を切り開く斬新さか。そのことが北条家が全国区の人気になれない理由の一つであり、ドラマの主役になりきれない理由の一つではないのか...と思う今日この頃です。
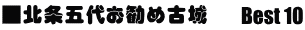
01 小田原城&総構(神奈川県小田原市)
02 石垣山城(神奈川県小田原市)
03 山中城 (静岡県三島市)
04 江戸城 (東京都千代田区)
05 八王子城(東京都八王子市)
06 滝山城 (東京都八王子市)
07 鉢形城 (埼玉県大里郡寄居町)
08 花園城 (埼玉県大里郡寄居町)
09 箕輪城 (群馬県高崎市)
10 松井田城(群馬県安中市)
(順不同)
江戸城は近世徳川家の姿ではありますが、古城の遺構を見たときにはさすがの内容です。八王子城は太鼓曲輪も含めて見学しましょう。花園城は初期の頃に訪れ、藪を払って出会えた堀切や竪堀に感動しました。当時は今以上に藪が凄くて大変でした。それだけに思い入れが強く、その後も定期的に訪問している。松井田城は雄大な山城で、一日いても飽きが来ません。入山するときは登山口に用意されるクマ除けの空き缶を体に巻き付けて.....。次点として、千葉県の本佐倉城や久留里城(+古城)も忘れてはいけません。
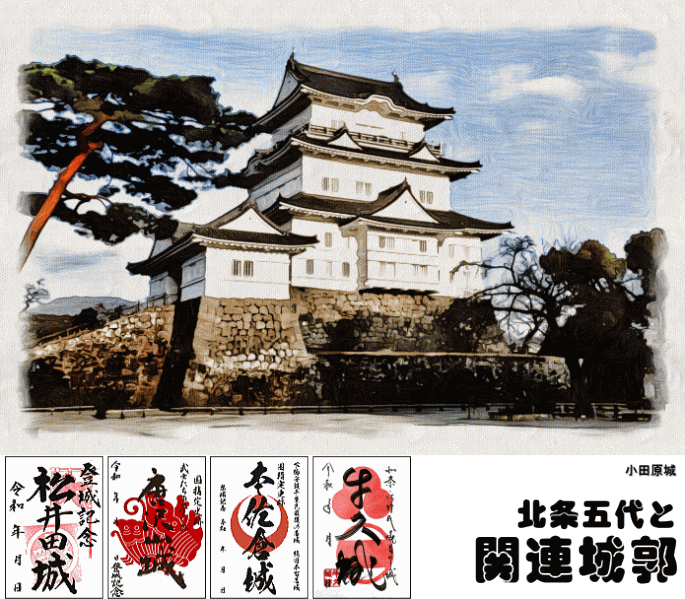

![]() 古城は左側に並ぶバナーから進んでください(まだまだ途中ですが)
古城は左側に並ぶバナーから進んでください(まだまだ途中ですが)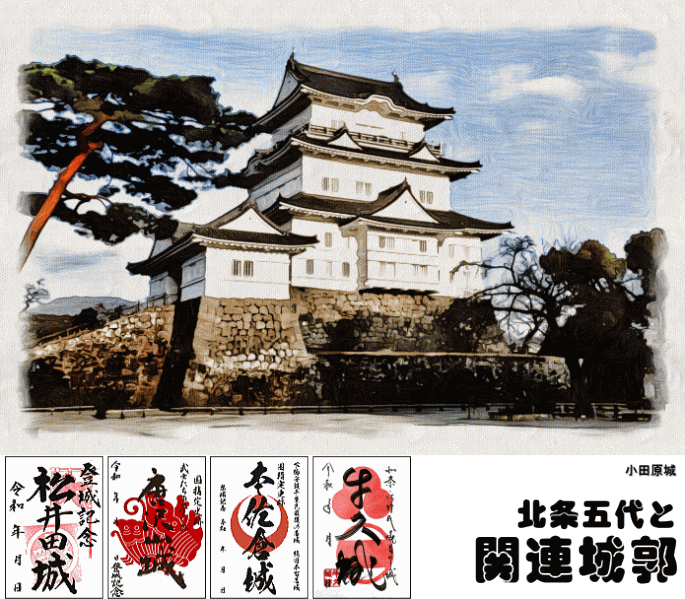

![]() 古城は左側に並ぶバナーから進んでください(まだまだ途中ですが)
古城は左側に並ぶバナーから進んでください(まだまだ途中ですが)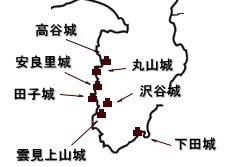 北条水軍の要 西伊豆地方
北条水軍の要 西伊豆地方
