reserve
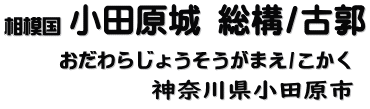
■小田原城総構/古郭 データ■
JR東海道線小田原駅下車 外郭周回4時間
史跡指定:国指定史跡
城の形状:総構
築城年代:天正18年(1590)まで続く
築 城 主 :北条氏康/氏政/氏直
廃城年代:外郭線の破壊は慶長19年(1614)頃か
城の別名:―
満足度 ★★★★

小田原城 小峯御鐘ノ台大堀切...息を飲むほどの光景が広がる
■小田原城総構/古郭 その歴史■
最初にお断りしておくと、「総構」と「古郭」は違う。総構は北条氏が小田原城を居城として以降に整備、拡張された防御を指す。のち豊臣秀吉との関係に緊張感が高まると、外郭線は城下町をも取り込んだ「総構」として完成されていく(一部に未完成も)。対して「古郭」は北条氏以前の大森氏時代の城の中心と伝えられ、北条氏が現在の本丸・御用米曲輪に主要部を移す前の曲輪とされる。ただし、その実態は明らかではなく、特に大森氏の時代の古郭については全くの不明と言っても過言ではない。現在、「八幡山古郭」と呼ばれ整備されている場所が、北条早雲や氏綱の時代の小田原城とされる。小田原城の中心が現在地に移されるのは、2代氏綱から3代氏康の時代と思われる。永禄3年(1560)に上杉謙信が、永禄12年(1569)に武田信玄がそれぞれ小田原城に兵を寄せているわけだが、氏康はその反省から外郭線の整備、拡張に取り掛かる。「相豆武三ヶ国之人足、寺領社領等迄、悉申付候」なる朱印状も見られ、堅固な城郭に向けた徹底した人足の差し出しを求めている。そして、時代は進み豊臣秀吉との戦いを覚悟した北条家は、さらなる城郭の拡張、いわゆる城下町も取り込んだ総構を築く。天正17年(1589)には自ら己丑大普請と呼んで人足を招集し、翌年の正月にも寅歳大普請と称し再び人足を差し出すよう求めるなど、大量に残されるこの時代の朱印状には北条家の焦りと言うか、悲愴な覚悟が読み取られる。小田原城の総構、巨大な土塁・空堀は総延長にして10キロにも及ぶとされているが、『小田原市史・城郭編』では登降や曲折の延長距離を考え9キロ余としている。戦国史上最大とも言われた総構は、北条家滅亡後に関東に入部した徳川家康の命で徹底的に破却されたわけだが、その全てを取り除くことは出来なかった。総構の一部は、450年経った今でも小田原の街を守るかのようにその雄大な姿を私たちに見せている。

小峯御鐘ノ台に残る巨大な堀切(左)と三の丸外郭新堀土塁(右)

■2021-3-19 7:40 八幡山古郭周辺■
八幡山は現在の小田原城とJR線の線路を挟んで反対側の城山に位置する。現在、県立小田原高校が建つ辺りがその中心とされ、以前の発掘調査では畝堀が出ました(現在は埋め戻される)。25年ほど前になろうか、僕は現地説明会に行ったことを思い出す。大森氏の時代、そして北条早雲が攻略した小田原城の主要部と考えられているが、古郭を伝える遺構は見られない。のちの総構の土塁は高校の敷地内にも散見されるようだが、そこは学びの舎ですので立ち入るのはいけません。古郭のうち、東曲輪と呼ばれる地は整備がされ公園となる。ここから小田原城の天守閣がよく見られるし、目を西の方に移すと豊臣秀吉が築いた石垣山がある。僕が古城めぐりを始めた30年前は、この地にはアパートが建っていた記憶がある。そのアパートの階段を上って天守閣の写真を撮った思い出が蘇る。この古郭東曲輪はJRの小田原駅から歩いて10分余でしょうか、ここからそのまま小峯の堀切に向かうか、一度城山を降りて総構の早川口二重遺構に向かうか、その判断に迷う。通常は小峯の堀切に行くことになると思うが、僕は早川口の遺構に向かいますね。多分、20分ほどは歩くと思いますが...。

▲八幡山古郭東曲輪に建つ説明板
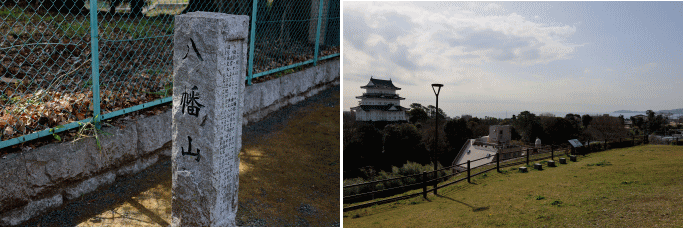
▲八幡山を示すブロック標柱(左)と整備がされた八幡山古郭東曲輪(右)
■早川口二重遺構 2021-3-19 8:51■
早川口遺構は、二重外張と呼ばれる土塁と堀を二重に配した構造となり、「早川口二重遺構」と言う呼ばれ方もされる。JR小田原駅から歩くと25分ほどになるでしょうか。箱根登山鉄道の箱根板橋駅の場合は5分ほどで済みます。ここも公園として整備がされますが、あまり訪れる人もいないのか静かな“とき”が流れている。周囲は住宅地ですので歓声を上げるのは控えたい。25年前は巨大なオニグモに遭遇して驚かされまして、早川口と聞くと土塁や空堀の遺構ではなく、そのオニグモを思い出すと言うトラウマがある。早川口は二重戸張の虎口と推定され、内側の土塁・空堀を基準にして、さらにその外側に土塁・空堀を併行させる構造を持っている。それにしても街中の平地によくぞ残されていたものだと感心する。

▲早川口遺構 二重土塁のうちの外側、窪みは堀道

▲ともに、早川口遺構
■2021-3-19 9:51 ちょっと休憩...毒榎平■
早川口遺構から再び来た道を戻って城山へ。今度は総構の白眉とも言える小峯御鐘ノ台の堀切に向かうが、小田原の駅から真っ直ぐに向かった場合は、坂道を歩いて25分かな。真夏の暑い時期だと朝がタラリタラリと流れ落ちるかと思います(早川口遺構からも25分ほどか)。その小峯の堀切の手前に休憩スポットとなり城山公園、通称「毒榎平」がある。ここは総構成立以前の小田原城の最西端とも言われ、発掘調査では巨大な堀も出ている。しかし、その名の由来でもある毒枝の栽培は伝えられていないとか...。では、何故この名が付いたのでしょうか。現在は城山公園となり、相模湾が眺められ、桜の時期は美しさも格別とか。そう思って桜の開花時期に合わせて総構見学をしたのだが、ちと早かったようだ。地元の住民なのでしょう、結構犬の散歩で訪れる方も多いですね。

▲毒榎平のブロック標柱(左)と城山公園(右)
■総構の白眉 小峯御鐘ノ台 2021-3-18 10:27■
小峯の大堀切は城山公園の西端に位置し、東堀、中堀、西堀の三本の堀切によって構成される。兎にも角にもその姿は圧巻で、小田原城総構の白眉と言っても過言ではない。25年前よりもさらに整備が進み、その全体像が見て取れるのではないだろうか。なかでも当時の様子が最も良く残る東堀は幅が約20~30m、深さは土塁の頂上から約12mあり、堀の法面は50度という急な勾配で、空堀としては全国的にも最大規模とも言われている。この堀切は小田原城の主要部へと続く八幡山丘陵の尾根を分断し、西側の守りを固める重要な場所ともなる。無駄にデカいと陰口も囁かれる北条氏の城だが、確かにビッグだ。北条氏の悲劇は“秀吉”と言う風変わりな男を相手にしたことだ。この男は無駄な力攻めはしない。時間は掛かろうが、相手が「参った」と言うまで城を囲みながら、その陣馬で日常生活を過ごす。せっかく人足を徴集して総構を充実させても、結局のところは秀吉には相手にされずに終わってしまった。

▲小峯御鐘ノ台 東堀切

▲小峯御鐘ノ台 東堀の土塁(左)と道路となる中堀(右)

▲小峯御鐘ノ台 西堀(左)とその土塁(右)
■2021-3-19 11:40 三の丸外郭新堀土塁■
今度は小峯御鐘ノ台の東堀から三の丸外郭新堀土塁へと足を進める。城山から相洋高校の方向へ10分も歩きませんね(バスが走る車道)。近くまで行くと案内板もあるので迷わないと思う。そして何が素晴らしいかと言うと、美しい芝です。こんなにも綺麗に整備されると、ここが「戦い」の場所であったと言う史実が吹っ飛んでしまう。問題は「外郭」の名があるため、この遺構が総構マップから漏れている場合もあると言うことです。僕は職場の仲間に“ある活”(健康のために歩くイベント)に総構を勧めているが、行かれた人はこの外郭新堀土塁は見ていません。これは由々しき問題だぞ~(怒)小田原市に怒ってみたりもする。

▲三の丸外郭新堀土塁
■水之尾口 2021-3-19 12:42■
水之尾口は小田原城総構の最西端であり、標高120mも最高地点である。さすがに小田原駅からここまで歩くとなると、足腰がイテテ...となるでしょうか。駅前からバスも出ていて所要時間は15分ほどです。僕は三の丸外郭新堀土塁からバスが走る車道を歩いたため、時間にして20分強と言ったところか。水之尾口櫓台の説明板も建つが周囲は畑、多分茶畑になるのかな。さすがに小田原城を訪れ、さらにここまで来る人は物好き以外いませんね。この水之尾口に対し、豊臣勢は宇喜多秀家や織田信包の軍勢が対陣したと伝えている。また小峯御鐘ノ台から水之尾口に至るルート(香林寺山西)には土塁も良く残され、僕にとっては絶好の散歩道とも言えるか。

▲水之尾口櫓台(左)と御鐘ノ台の土塁(=香林寺山西)
■2021-3-19 13:15 神秘の世界 稲荷の森■
水之尾口から歩くと20分...、小峯御鐘ノ台からは10分強でしょうか。竹林の中に残される幻想的な大空堀が「稲荷の森」です。幻想的と言う表現を使いましたが、神秘的と言った方が相応しいかな。25年前は竹藪に覆われて荒れていましたが、綺麗に整備をされ見学しやすくなりました。堀の深さも結構なもので、こうした堀に出会うと堀底に降りたくなるのは自然の心理か。踏み跡を辿って降りていくが、一部に崩されている箇所もあるので対策が必要だと思いました。空堀の端っこにルートを作る方が現実的かと...、「降りるな」だけでは遺構は守れません...反省、猛省です。小峯御鐘ノ台の堀切に次いで、僕のお勧めなのだ。

▲稲荷の森 巨大な空堀
■山ノ神堀切 2021-3-19 13:55■
稲荷の森から5分ほど歩くと、山ノ神堀切がある。この辺りは農道で民家もチラホラです。女性の一人歩きは日が暮れないうちは大丈夫でしょうか。もう少し進むと住宅街に出ますので、危ないと思ったら全力疾走で逃げてくださいませ。僕は親爺なので煎餅を食べ、“お~い、お茶”を飲みながらのんびりと歩きました。この堀切は、谷津丘陵上の通行を制約するために設けられていたと言われ、小田原城の北側を守る重要ポイントだそうです。江戸時代は山番と呼ばれる門番が配置され、朝夕はその門を閉じていたと伝える。僕が訪れた時点では発掘調査などまだ行われたことがなく、堀切の深さなどは定かではないと説明板に書かれていた。それでも表面を見ただけでも規模の大きさは伺い知れる。それと綺麗で見学しやすいのが良かった。

▲写真は、山ノ神堀切
■2021-3-19 14:15 城下張出■
山ノ神堀切から5分ほど歩くと、城下張出が見られる。地形を利用して総構のラインから貼りだす形で突出させた部分を呼ぶようだ。戦国期の古城の土塁に見られる“横矢掛かり”と同じ仕様で、寄せ手に対し横から矢を射る構造です。住宅地に囲まれ、パッと見ると「?」の記号が頭の中に浮かぶでしょうか。僕の頭も例外ではなく、「?」でした。地図と照らし合わせるとイメージが湧くかと思う。ここまで下ってくると、周囲は住宅地なので中世の面影も消え去る感じでしょうか。朝から6時間ほどは歩き続けたかな。僕は昼食を摂りながらの散策で、しかも古城大好きなので時間を要すが、総構そのものは4時間程度で回れるかと思います。
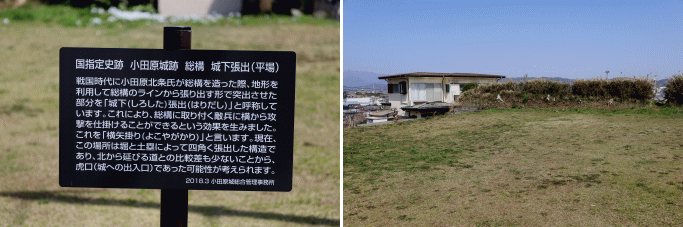
▲城下張出の説明板(左)とその姿(右_写真で見ても「?」)
■蓮上院大土塁と江戸口見附 2021-3-19 15:25■
平地に残る総構の代表格が、蓮上院大土塁ですか。小田原駅からバスの場合は10分余、徒歩の場合は20分ほどで行けるでしょうか。土塁は鉄柵と言うか、金網で保護されていまして、その金網に足を掛けて写真を撮りました。間近で見るとそれなりに迫力があり、途中で土塁が崩れた個所は空爆の跡だと説明板にはありました。豊臣秀吉の空爆攻撃ではなく、第二次世界大戦のときの空爆です。その大土塁から5分歩くと総構の最南を守る江戸口見附になる。秀吉の北条攻めのとき、徳川家康が陣を張った今井陣場にも近く、家康が日々参拝したと伝える山王神社が近くに建つ。江戸時代は小田原城下に入る東海道の東の出入口として、重要な門としての役割があった。今は小さな公園になっていました。

▲蓮上院大土塁

▲蓮上院大土塁(左)と江戸口見附(右)

※コロナ禍...2020年頃から国内を襲ったコロナ・ウイルスの脅威。人々の接触がウイルスの蔓延にも繋がると言われている。いつまで続くのか...。
※小田原城総構は小田原市でも積極的なアピールがされている。小田原市の公式サイトでは総構マップが作成されていたり、様々な企画も用意されることもあるので覗いてくださいませ。
